「数学のセンス」「数学的思考力」「数学的発想力」……。どれもこれも持ち合わせていないから数学が力が伸びない……。そんなことはありません。数学のセンスを後天的に身につけることは誰にでも可能です!
「センス」という言葉を広辞苑で調べるとこう書かれています。
物事の微妙な感じをさとる働き・能力。 感覚。
『広辞苑』
数学に限らずですが、センスというのは生まれつき持ち合わせているものではなく、後天的に身につけていくものだと思っています。
例えば、ファッションセンスであれば、様々なファッションメディアで髪型、服装や着こなし、アクセサリー、メイクを見て、記事コンテンツの情報から流行りや「なぜ、イケているのか」を学び、自分でも真似したり、アレンジしたりして、それから周囲の人やSNSからの反響から、これはウケている、まあまあ、ダサいなどの「微妙な感覚」の違いを学びセンスを磨いていきます。
スポーツでも同じです。サッカーを例に出すなら、様々なプレイの中での成功と失敗の経験から学んで考えて試行錯誤する中でサッカーセンスは磨かれます。サッカーだけではなく、トップアスリートは類稀な身体能力ともに、言語化能力が非常に高いと感心します。インタビューや対談動画を観ても自分の一つ一つのプレーやゲームの状況を、素人でもわかるよう即座に説明できる方が多い印象にあります。
2つの例を出しましたが、センスを磨く過程の中で大事なことは「学び」「考える」ということです。
しかし、「学ぶ」も「考える」も具体的な動詞のように錯覚しますが、非常に抽象的な動詞だと思っています。ですから、数学のセンスを身に付けるため、「学び」「考えて」もらうために具体的なアドバイスを送りたいと思います。
まず「学ぶ」と「考える」を少しだけ具体化すると「学ぶ」は「知識を覚える」、「考える」は「試行錯誤する」と「視野を広げる」になると僕は思っています。
ここからは数学の話に限定していきます。
数学の知識を学ぶ上で欠かせないのが教科書です。それから『青チャート』などの解法網羅系参考書です。しかしこの記事を読まれている方は、完璧ではないにしてもこれらは概ねやり込んでいるのではないでしょうか。
僕が今回薦めるのはこの2冊です。特に『青チャート』や『Focus Gold』をやってみたけれど、偏差値60前後で伸び悩んでいたり、東大、京大、東工大、一橋大レベルの問題になると手が出ない、という方に特におすすめです。
『計算のエチュード 戦略編』
たかが計算と侮ってはいけません。計算が速ければ、計算にかかる時間を省略できます。その分を考える時間に充てることができます。また正確性が増せば、正答率も上がって得点力が増すのは言うまでもありませんが、途中の計算の躓きによる「焦り」がなくなって精神的な余裕も生まれます。
この参考書は、計算のコツや工夫だけではなく、数学の式や問題の見方、分析・考察の仕方が学ぶことができ、この1冊を終えた後に『青チャート』や『Foucus Gold』を復習すると、新たな角度で例題を学びなおすことができお勧めです。ボリュームも解答込みで220ページほどと1~2か月程度で取り組むことができます。
この参考書は、数式や関数といった「定量化」されたものを図形的に「定性化」して視覚化・具体化して、これをきっかけに解答を足掛かりを作る手段を教えてくれる参考書です。エチュードより薄く難易度はやや高いのですが、そもそも1周目で理解できるような代物だと著者も想定していません。2周、3周とやる中で自分のものにしていってください。
この2冊はボリュームと難易度の違いこそあれ、内容の重複はほとんどありませんので、ぜひ2冊とも取り組んでみてくださいね。


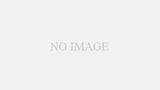
コメント